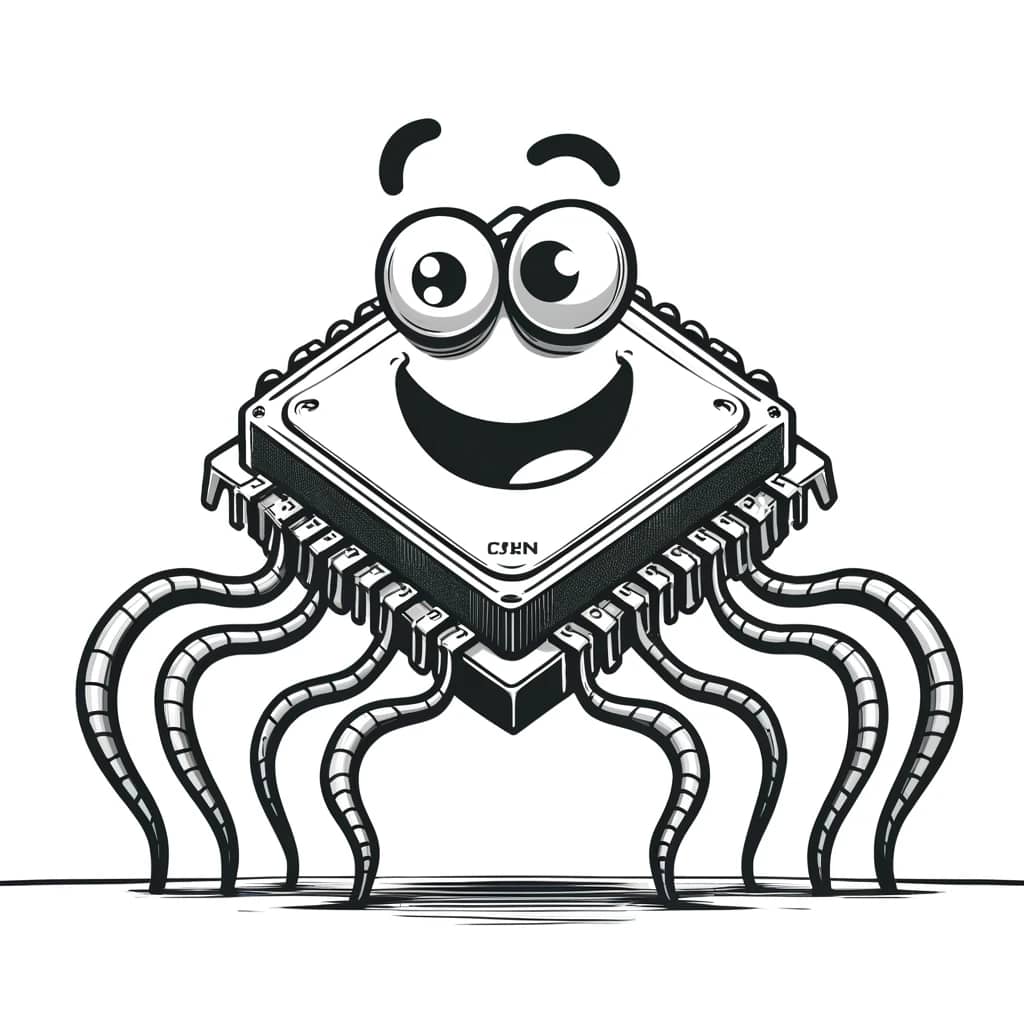序論
オブジェクト指向言語と聞くと今まで for 文や if 文を回すだけだった者は身構えてしまうかもしれないが,わかってしまえばどれも同じレベルだ.本記事では,Python で出てくる基本的な用語を通してオブジェクト指向を少し理解してもらおうと思う.また,本記事は何かまた思いついた時にしれっと更新しようと思う.
本論
オブジェクト指向とは,文字通り「オブジェクト」を中心にプログラミングしていると考えた方がわかりやすい.この「オブジェクト」はなんと処理(機能)も含むのだ.つまり,手続き型の言語が「処理」を記述したものだとしたら,オブジェクト指向型の言語はまさに「オブジェクト(物,製品)」を記述していると考えるのだ.
以下に,基本概念を列挙する.
- クラス(Class):
オブジェクトの設計図.あくまで設計図だから Class を宣言した後に,実態(Instance)を持たせないと使用できない. - オブジェクト(Object):
クラスから生成される実態(Instance).クラスに基づいてオブジェクトが作成される. - 属性(Attribute):
オブジェクトが持つ要素.同じクラスから生成されていても,オブジェクト毎に属性を持つ.クラス内で “self.” とついている変数,パラメータ達が該当する. - メソッド(Method):
オブジェクトが持つ処理.オブジェクト毎に処理される.クラス内で “def” で定義される.呼び出すときに () 付けるの忘れがち.普通の関数とは分けて言う.
以上が基本概念だ. 以下で具体的なコード例を用いて説明したいところだが,Wordpress の投稿画面でどうやってコードスニペットをはるのか分からなかったので,近日追加する.
結論
研究での使用を前提としたとき,Python の基本的な用語なんてこんなものである.まずはここら辺を意識しながらコードを書いてみると良いかもしれない.